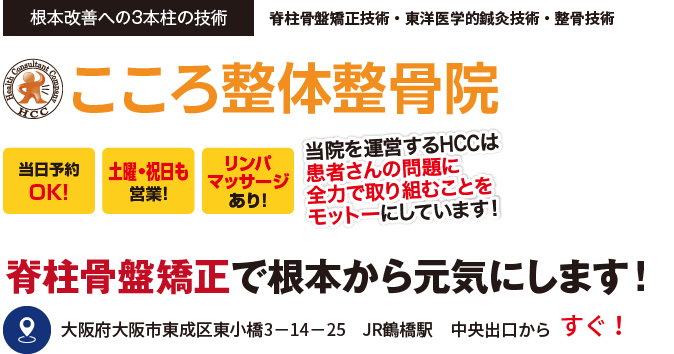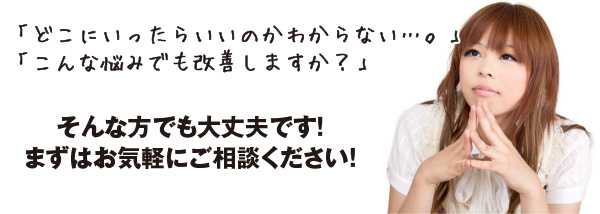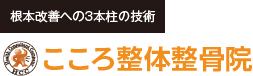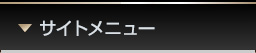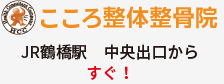水分と毒素の関係
2024.07.23
こんにちは!
大阪市東成区東小橋の「鶴橋こころ整体整骨院」で鍼灸師をしております、石本と申します。
本日も鶴橋こころ整体整骨院のブログをご愛読いただき誠にありがとうございます!
7月も後半に入り、恐ろしいほどの猛暑に日本列島は包まれていますね!
危険な暑さに熱中症アラートが鳴り止まないこの時期ですが、暑さによる発汗、外気の温度により蒸発していく皮膚表面の水分で体内の水分はどんどん減少していきます。
そうなると恐ろしいのが脱水症状です。
人間のからだは体内に蓄える水分量と、体外へ放出する水分量とのバランスで体液を調節します。
このバランスが崩れたときに脱水症状が起こります。
発汗、下痢、嘔吐など様々な原因はありますが、脱水症状が起こると意識か混濁し、頭痛、吐き気、めまいを引き起こします。
こまめな水分補給が必要になりますので本日は脱水症状をどうやって予防していけば良いのかを説明させていただきます。
まず大事なのは水分補給です。ペットボトルなど持ち運びやすく量がわかりやすい容器にいれた水分を常に準備しておく必要があります。
脱水症状には自覚症状が現れる前段階の前脱水と言う状態があります。
体内の水分が3%減ると脱水症状に対して、2%減っている段階を前脱水と言い、いわゆる夏バテのような倦怠感を感じている状態がこれにあたります。
体が重い、ダルいといったような症状を感じたらその時点で水分をとらなくてはいけません。
特に注意が必要なものとしては高齢者の脱水症状です。
お一人で暮らしている高齢者の方などエアコンを使わない方は知らず知らずのうちに室温が上がっていることに気付かず、自覚症状が感じられない場合がおおいです。
空調による室温調節と決まった時間に水分補給を行うことが大事です。
これからの時期はどんどん気温もあがり、発汗が激しくなることが考えられます。
これくらいならと自分の身体を過信せず、体調管理と健康維持に注意していくことで、元気に夏を楽しむ努力が必要です。
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
当院で取り組んでいる「毒出し整体」は吸い玉を使い体内毒素が体外へ排出しやすい状態か
否かを見定めます。
その時にくっきりと体表での反応が出ない場合があります。
それは体内の水分の循環がうまくいっておらず、毒素を流す力が
弱くなっている可能性があります!
水分が少ないと体内の毒素を動かしてもうまく循環ができず、また毒素が沈着しやすい体になってしまいます。
これからの季節はまだまだ気温の上昇が考えられます。
皆様もしっかり水分をとってこの猛暑を乗り越えて下さい!
ご予約はこちらから
毒素を溜め混みすぎると
2024.07.16
毒素を溜め込みすぎると
こんにちは!
鶴橋こころ整体整骨院の鍼灸師石本です!
私の愛する東成区東小橋にも夏がやってきましたね。
猛暑がやってくるとフーッと気が遠くなるような感覚に襲われたことはありませんか?
それは暑さで自律神経が興奮し、交感神経が優位になり筋肉が緊張しすぎて脳への血流が途絶えている恐れがあります。
そして、暑さによる発汗で体に必要な水分が不足し脱水状態を起こしている可能性も考えられます。
万が一このような状態に陥った際には休息とクールダウンが必要ではありますが、日頃から疲労物質を溜めすぎない、水分が体に循環する環境を作ることが大事です。
疲労物質や水分潤滑の妨げになるものがいわゆる毒素という物です。
毒素は日常生活の中でも、外気や食物から体内に入ってくるものです。
排泄や発汗で体外に排出して健康状態を維持する必要がありますが、体調などの影響でなかなかうまくいかない時もあります。
そのため、日頃から体内環境を整える必要があります。
我々はこの体内環境を整える方法として「毒出し整体」を推奨しております。
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
吸い玉両方で毛細血管に沈着した疲労物質を動かして、足つぼを刺激する足裏マッサージで排出しやすい状態を作る方法です。
現在多くの方にこの施術を受けていただき、こんなに自分の体に毒素が溜まっていたのかと驚かれるお声をお聞きしています。
これから訪れる猛暑は非常に危険な暑さが予測されます。
元気に皆様が真夏を乗り越え、活躍の場を広げてくれることを私たちは望んでいます。
当院の推奨する「毒出し整体」を是非ともご体験しに来てください。
ご予約はこちらから
熱中症と毒出し
2024.07.09
熱中症と毒出し
こんにちは!
鶴橋こころ整体整骨院のブログをご覧いただきありがとうございます!
本日も大阪市東成区東小橋よりおとどけします!
この数日の異状な暑さ、皆様お体大丈夫ですか?
この時期に最も恐いのはやはり、熱中症ですね。
熱中症とは高温多湿な環境に私たちの体が順応できなくなっておこる反応の総称です。
もしこのような症状が起こったら
めまい
立ちくらみ
顔のほてり
筋肉痛や筋肉のけいれん
体のダルさ
吐き気
汗のかきかたがおかしい
体温が高い
皮膚の異常
などはすべて熱中症の初期症状です。
すぐに体を冷やす、水分をとるなどの処置をしないと
まっすぐ歩けない
ろれつが回らない
吐き気がする
など、中枢神経障害に類似した症状を引き起こします。
熱失神とも呼ばれる状態で、暑さで体温が急上昇すると熱を逃がすため皮膚の血管が広がります。その結果、全身の血流量が減り、血圧が急激に低下します。
血圧が一気に下がってしまうと脳への血流が減るため、熱失神がおこります。
血圧の低下と同様に恐ろしいのは汗が大量にでる、または全く汗が出なくなる事です。これは体温調節が正常に働かなくなっていることを意味し、最悪の場合脳への深刻なダメージを残すことや命を落とす可能性もでてきます。
熱中症にならないためには日頃から疲労を溜めないことが大事です。
当院の毒出し整体は疲労の原因となる毛細血管に蓄積した毒素を体表まで動かして排出しやすい状態を作ります。
 鶴橋こころ整体整骨院 熱中症 毒出し
鶴橋こころ整体整骨院 熱中症 毒出し
毒素をどかすことにより作りたての新鮮な酸素と赤血球がいっぱい含まれた血液が全身を巡り自律神経を整えるため、深い睡眠がとれるようになり、日頃のストレスや疲労を軽減する効果が生まれます。
熱中症は睡眠不足や栄養失調で体が弱っている人に発症することが多いため、日頃からのヘルスケアに毒素出しを選択されてはいかがでしょうか?
ご予約はこちらから
毒出しと美容
2024.07.03
こんにちは!
鶴橋こころ整体整骨院のブログをご覧いただきありがとうございます!
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
当院で今取り組んでいる「毒出し」について毒素を体内から排出することによるメリットについて本日はお話させていただきます。
本日ご紹介するメリットはズバリ「美容」です。
美容と毒出しは非常に関係が深く、2000年代初頭におとずれたデトックスブームでも体に溜まった毒素を排出することにより
・血行がよくなる
・新陳代謝がよくなる
・腸の活動がよくなる
・太りにくくなる
・冷え症、むくみ、肩こりが解消される
・自律神経を整えイライラを抑制できる
と、どれをとっても良いことだらけです!
広義における「毒素」の種類は大きく分けて3つになります。
老廃物
飲食物の栄養素が体内で吸収されたあと、最後に残る不要物のこと
(腸内細菌の死骸、尿素、尿酸、アンモニア、クレアチニンなど)
有害ミネラル
サプリメントなどで一般的に知られているミネラルとは別に、人体に様々な障害をもたらす有害なミネラルの総称。
有害金属とも呼ばれる
(水銀、鉛、アルミニウム、カドミウム、ヒ素、ベリリウム、ニッケルなど)
有害化学物質
環境ホルモンなど、生体のホルモンの働きを狂わせる人間が作り出した化学物質
(ゴミの燃焼時に発生するダイオキシン、塩化ビニールに含まれるフタル酸など)
これらの毒素は体内に蓄積すると代謝活動を妨げ、筋収縮をしにくくするので表情筋の筋力低下、痩せにくい太りやすい体質を生み出してしまいます。
こうならないためにも日頃からのヘルスケアは大切です。
食事
睡眠
水分
をしっかり取る事と皮膚の下にある毛細血管をしっかり動かして毒素を流さなくてはいけません!
毒出し整体は吸い玉で毒素を体表に浮かび上がらせて毛細血管の潤滑を良くする働きがあります。
そして重力で下に下がった水分や血液を足裏マッサージでしっかり戻し、尿や便として体外に排出しやすい体質をつくることができます。
美しくなるにはまず健康でいなくてはいけません!
ぜひこの機会にご体験なさってください!
ご予約はこちらから↓
https://reserva.be/tsuruhashikokoroseitai
Google検索 https://g.co/kgs/L1B4GRk
身体の解毒器官の働きは万全ですか?
2024.07.02
身体の解毒器官の働きは万全ですか?
肝臓は人体における最大の内臓であり、代謝や解毒、ミネラルやビタミンや血液の貯蔵庫としても
働く重要なところです。
日常のストレスや怒り、またはアルコール類や添加物など様々な処理に働き続けてくれる肝臓を
東洋医学的にその肝臓の気を高めてくれるツボの存在があるとしたら知っておきたくないですか?
ちょっと自分自身でマッサージすることにも使えますね!
鶴橋こころ整体整骨院で受けることができる毒出し整体では
この肝臓の気を高めることができる
「大敦」(だいとん)」
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体 大敦
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体 大敦
写真の赤丸の場所で、足の親指の爪の外側の角にあるツボです。
肝臓にストレスがかかって働きが悪くなっていると、解毒機能が低下し血中に毒素が
流れてしまうそんなことの改善に働きかけることで肝臓が元気になり働きがよくなる秘孔です。
しかも、耳鳴りや難聴にも効果ありなんです。
〇〇〇整体整骨院では
ここをしっかりと網羅した毒出し整体になっています。
病気に変わる前にちょっとした体の疲れとともに内臓の働きを高めるような施術があれば便利です。
病気になってから痛みやら休養やらのリスクを背負って処方箋をもらうのと
病気になる前にリスクを背負わずにケアすることができる予防線なら
どちらがいいでしょうか?
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
処方箋は薬屋さんしか儲かりません^^;
予約はこちらから↓
https://reserva.be/tsuruhashikokoroseitai
Google情報 鶴橋こころ整体整骨院
https://g.co/kgs/m1dQDKs
毒出し習慣!
2024.07.01
 鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 毒出し整体
こんにちは!
鶴橋こころ整体整骨院です。
季節の移り変わりは早いものでもうすぐ夏はやってきますね!
大気や気候の変化とともに体調も急激に変化します。
突然の体調不良の予防や健康維持のために我々は「毒出し」という整体法に辿り着きました!
体に蓄積した毒素を体外に排出すれば新しい新鮮な血液が全身を巡り、ホルモンバランスや自律神経の調整にもつながります。
今回は日頃から毒素を溜めない生活習慣についてお話ししたいと思います。
まず、体内に蓄積した毒素を取り除くには排泄機能を使うことです。
排泄機能として排尿に関係する腎臓、排便に関係する腸が正常に機能することが大切です。
そのために共通して重要になるのが水分です。
1日の水分摂取量としての目安としては食事から1リットル、飲み物から1.5リットルの合計2.5リットルは理想です。
ただし、飲みものからの1.5リットルの水は一度に飲んでも体が吸収できません。
逆に胃に負担をかけてしまうこととなるので、1回の摂取量をコップ1杯分とし何回かに分けて摂取すると体に負担がかかりません。
水を使ったデトックス法は飲むだけではありません。
お風呂でのシャワーも活用できます。
老廃物を集める機関としてリンパ節があります。このリンパ節を刺激し、リンパの流れをよくすることも老廃物を排除する働きになります。
まず温かいシャワーを鎖骨付近にあて、続いて足のつま先から膝、太もも、股関節へ向かってシャワーを当てます。
次にての指先から手首、肘、脇の下にゆっくりシャワーを当て、最後にお臍を中心に時計まわりにシャワーを当ててお腹を刺激します。
その他にもお風呂でできるデトックス法として38度から40度のお湯で半身浴をすることもおすすめです。
新陳代謝が上がり発汗により老廃物を排出することができます。
この様に内臓の働きやリンパの流れをよくすることが毒素を溜めない生活習慣として大事です。
これらの作用として自律神経が大きく関係します。
腎臓は特に自律神経の影響を受けやすいので自律神経神経を調整できる鍼灸治療や東洋医学が毒素が溜まりにくい体質作りには必要です。
当院の「毒出し整体」は東洋医学で太古から使われている吸い玉と浮腫やむくみとして毒素蓄積が現れやすい足部の足底マッサージを併用したどんどん毒素を排出するための施術です。
最近いくら寝ても眠たい、やる気が全く出ないという方!
毒素に体を蝕まれている可能性がありますよ!
ぜひ毒出し整体をご体験なさってください!
ご予約はこちらから↓
https://reserva.be/tsuruhashikokoroseitai?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYM2L7awiMNL6LB1cAJ4KrjOo0hsI6ECRPXS1GbZX_Oa3sKddjClDZ0l0Y_aem_AUVb0HxL2vv8iey_hOqUtbc3oI8TeBeLH_7X_szN1qg1_Z6xmdjT0m6ix8eEQJIXEb95Qldhvz-HzSXCQyPJGWtL
毒素って何?
2024.06.22
こんにちは、鶴橋こころ整体整骨院のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
本日は最近よく耳にする「デトックス」「毒素」というものについてお話させていただきます。
まず毒素とは何なのかをご説明します。
体内に溜まる毒素とは
体内の毒素には呼吸や食事により体外から体内に運ばれるものと、体内で発生するものがある
体外から入ってくる毒素
・化学物質や有害ミネラルで大型の魚に含まれる有機水銀
・古い水道管を通った水に含まれるニッケル
・缶詰や鍋のアルミニウム
・タバコの煙、排気ガス
・野菜に付着した残留農薬や除草剤
・食物に残留したカビ毒
体内で発生する毒素
・腸内細菌が腐敗して発生するアンモニアや硫化水素
・各臓器が行う代謝活動の過程で発生する活性酸素や毒性のある代謝物
通常は、抗酸化機能や解毒機能で無毒化できるが、機能が衰えていると有毒性となり蓄積し排出しなくなる
解毒を行う臓器として肝臓と腎臓が解毒の要となる
排泄ルートとしてまず、食事などで体内に侵入した毒素は腸に吸収され解毒臓器である肝臓に運ばれ、ここで解毒処理が行われます。
その排泄物は胆汁として胆囊に運ばれて再び腸に戻り便として排泄されます。
これを腸管循環と言います。
世の中の認知
デトックスという観点から腸の働きをよくすることが重視されており「腸活」という言葉が生まれている。
腸を活発化させるためにプロバイオティクスやプレバイオティクスを含む腸内の善玉菌を増やすサプリメントなどが出ている
金額にして30日間分で平均3000円
整骨院やエステでの腸活デトックスコース8000円〜13200円
腸内環境を整えることが重視されているが解毒作用を高めるため肝臓機能を高めることも必要であり
肝機能は自律神経の影響を最も受けやすい臓器と言われており自律神経を調整する治療法として鍼灸治療の効果が期待されています。
当院では鍼灸治療による体内環境の改善を考え、吸い玉療法を推奨しています。
吸い玉は体内に溜まった毒素を体表に集めて排出しやすい状態に持っていくことのできる治療法です。
体質改善の視点からも効果があり、美容や健康にも非常に良いです。
7月に姿勢分析、吸い玉療法の無料体験実施します。
この機会にぜひご相談、ご体験ください。
ネットご予約はこちらから↓
毒だし整体の予約はこちら
 鶴橋こころ整体整骨院 吸い玉療法 自律神経調節 鍼灸治療 毒出し整体
鶴橋こころ整体整骨院 吸い玉療法 自律神経調節 鍼灸治療 毒出し整体