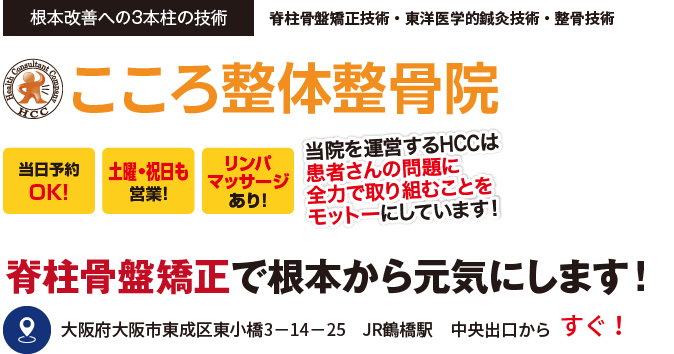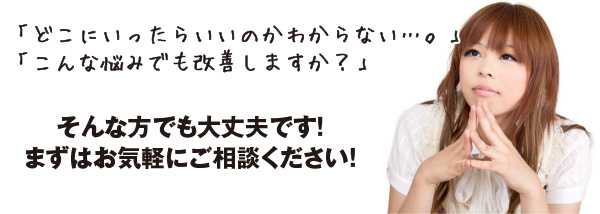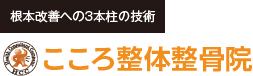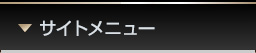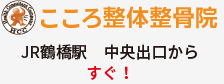お身体冷やさないように!
2024.02.07
こんにちは、いつもご愛読ありがとうございます!
鶴橋こころ整体整骨院です!
最近気温の低下が著しいですが、皆さまお体におかわりございませんか?
本当に寒くて外出や朝起きるときにも辛いですよね。
着ていく服やアイテムにもかなり気を遣わなくてはいけなくてこの時期は困ってしまう事が多いですね。
気温の低下は体温の低下につながり、身体活動の低下、免疫力の低下につながります。
そこで本日は簡単にできる寒さ対策についてお話ししたいとおもいます。
まず、体温が一番ひえてきやすいのは指先や足先といった末端部分です。
身体の末端には誰しも毛細血管があります。
毛細血管が冷えにより緊張し、活動が遅くなると抹消にいった血流が心臓に戻りにくくなり血圧の上昇にもつながります。
そのために手袋や靴下なども出来るだけ分厚いもの良いと考えられ、さらに手首、足首そして首と言った大きい血管が通っているところもしっかり温めてあげるとより効果的です。
東洋医学の見地からも手首、足首、首には自律神経を整えるツボがたくさん存在し、お灸などで温めてと血管の拡張により身体を内部から温めることができます。
体温の低下は人間から活発性を奪い、運動性がなくなることにより、感染リスクだけでなく、ギックリ腰などの急性疾患を引き起こすことが考えられます。
私も推奨していますが、急な動きによる痛みのトラブル解消法として、まず朝の起床時は一気にベッドや布団から起きない。
一見だらしなく思われる方もいらっしゃるのではと思いますが、布団の中でモゾモゾする時間を作ったほうが急性腰痛だけでなく高血圧の予防にもなります。
手足をゆっくりうごかす事で体幹の筋肉も刺激され少しずつ筋肉の緊張が解けた状態で起きる方が身体への負担は少なくて良いですよ!
皆さんも外出時、そして室内でも寒さや冷えには十分に注意して、健康なからだを普段の生活から維持できるよう工夫してみてくださいね。
まだまだ寒い日が続き私たちが生活する大阪でも珍しく雪が降るときもありますが、暖かい春はもう目の前です!
春は新しいスタートの季節、皆さまが元気に健康で春の日差しの中過ごしていただける事を願い、日々の施術も鍛錬し、お身体のお悩みにお応えできるよう今後とも精進いたしますので、これからもどうぞよろしくお願いもうしあげます!
肩こり
2024.02.07
こんにちは、こんばんは鶴橋こころ整体整骨院です。寒い日が続きますが、今年は暖冬だそうですが、寒さがこたえますね。インフルエンザも流行っているので体調には気をつけて年始から体調を壊さないようにしてくださいね。
さて今回は肩こりの原因やネットやテレビでいろいろといわれている、ほんとの事と嘘の事を話ていきたいと思います。
まず肩こりは人間特有の感覚であると言われています。なぜなら二足歩行をしているからという事です。四足歩行では手が地面についているため安定していますが、二足歩行になると腕が肩からぶら下がっている状態になります。重力があるので筋肉が常に腕を肩にひっぱりあげていないと肩が外れてしまいます。ですので肩周囲の筋肉は力が常に入っており筋緊張が起きやすい状態になりやすいのです。
ただ肩こりがある人や無い人もいますよね?これにはいろいろと憶測がありますが、基本肩こりがないと言っている人も肩の筋肉を触ると硬いです。ですので単純に肩の筋肉が硬くなっている事に気づいてないだけの可能性があります。凝りやすい人には骨格的要因(なで肩、いかり肩)や精神的要因や生活習慣の要因などが上げられます。精神的要因では、緊張がしやすい人や怒りっぽい人が肩が凝りやすいと言われています。生活習慣では、皆さんの想像どうりパソコンなどが例にあげやすいと思います。
ネットでは肩こりは病気!って言っている文章がありますが、病名には肩こりという名称はありません。
医学的病名をつけるなら頚肩腕症候群になります。これは首や肩に関する病名や疾患名がないのに痛みや違和感がある場合につけられる疾患名です。
よく首をマッサージすると筋肉を傷めたり重大な病気になる恐れがありますと記載されいる記事などを見ることがありますが、基本的には常識を逸脱した力で首を押すなどしない限り起きることはありません。首に頚椎症やヘルニアなどもともと重大な疾患を持っていてマッサージなどを受けることにより悪化する可能性はあるかもしれませんが、整骨院の先生は解剖学、生理学、病理学など医学の勉強をしてその可能性があるのかなどを診察するすべを知っています。この勉強をして国の決められた試験を受かる事で国家資格をもらえるので基本的には異常が起きることは考えずらいです。ただ先生により知識と技術の差があるのでちゃんと説明して治療をしてくれるところをお勧めいたします。
感染症予防
2024.01.12
こんにちは、鶴橋こころ整体整骨院です。
急激な気温の低下で皆さまは体調など崩しておられたりしませんか?
気温の低下は体温の低下を呼び、免疫力の低下をおこします。
当院では免疫力を上げるためにリンパマッサージを推奨しておりますが、そもそも免疫力ってなんなの?
と疑問に思われる方も多いのではとおもいます。今日はこれからの季節、コロナウイルスやインフルエンザ、そして風邪予防のためにも、免疫についてのお話しです。
まず免疫力とは何かというお話をさせていただきます。
免疫力とはウイルスや細菌などの病原体やがんから体を守るための身体の防御反応です。
わたし達の周りには目に見えない細菌やウイルスが空気中を飛び交い、風邪やインフルエンザ、そしてコロナウイルスに感染し体調を崩してしまうという事がおこります。
病原体の身体への侵入を防ぐ働きが免疫です。
目や鼻、喉や腸といった粘膜組織、そして身体の中の免疫組織が24時間働き続け病原体の侵入を食い止めます。
免疫のシステムは2段階に分かれます。
1、ウイルス、細菌の侵入を防ぐ
2、侵入してきたウイルスと戦う
ウイルスを身体に侵入させない為に働くのは粘膜免疫です。
粘膜免疫が働くのは目や鼻、喉や腸など粘膜を介して異物が体内に侵入するのを防ぎ体外へ出してしまうことで病原体による感染を防ぎます。
粘膜免疫を突破して体内に侵入してきた病原体が入り、増殖してしまうと感染が始まります。
体に侵入してきたウイルスには全身免疫が働き、免疫細胞が働き、病原体を捕らえて排除します。
病原体を捕らえるのは自然免疫、捕らえて排出するのは捕得免疫と言います。
病原体の性質を見極め、熱に弱い病原体なら発熱する、下痢などで素早く体内から排出するのも捕得免疫の働きです。
これらの免疫の力、免疫力を上げる為に必要なのは、身体を温める、適度な運動を行うなど新陳代謝を上げて、適度な発汗を促すと免疫力がアップする結果が出ています。
まだまだ不安を胸に秘めている方も今の世の中では多いと思いますが、規則正しい生活をおくり、バランスの良い食事、十分な睡眠をこころがけ元気に健やかな日常を送りましょう。
当院では頚肩腰などの痛みに対する施術だけでなく健康増進のためのアドバイスや指導も行っています。
どんな小さな事でも遠慮なさらずドンドン聞いてくださいね!
寒い時ほど要注意 こむら反り
2024.01.09
足がつる、いわゆる「こむら返り」の経験は誰にでもあると思います。
運動時だけでなく、就寝中に突然、足がつった驚きと痛みで目が覚めることもありますが、おさまるのをひたすら待つくらいしか出来ないのは非常に辛いものです。
「つる」とは、足や手などの筋肉が伸縮バランスを崩してしまうことで、異常な収縮を起こし、元に戻らない状態をいいます。
一般的に、急に体を動かしたときに起こりやすい症状ですが、栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起きることがあります。
たまに発生するくらいならそこまで気になりませんが、足を酷使させたわけでもないのに、生活に支障をきたすほど頻繁に起きる場合、筋肉疲労以外にどんな原因が考えられるのでしょうか。
こむら返りや足がつる原因や対策について詳しく解説していきます。
こむら返りとは
ふくらはぎに起きる筋肉のけいれんの総称です。
足がつることもこれにあたります。
基本的には病気ではありません。
ふくらはぎの腓腹筋が異常な緊張をおこし、筋肉が収縮したまま弛暖しない状態になり、激しい痛みを伴う症状です。
ちなみに、こむらがえりの「こむら」はふくらはぎのことを指します。
その名の通り、ふくらはぎに多く起こりますが、実は、足の裏や指、太もも、胸など、体のどこにでも発生します。
運動中や就寝中に発症することが多く、妊娠中や加齢によっても起きやすくなります。
こむらがえりを起こすと、強い痛みを伴いますが、ほとんどの場合は数分間でおさまります。
どうしてこむら返り(足がつる)は起きるのですか?
大脳から発信された信号が脊椎中の神経系を通り、ふくらはぎへと直結する末梢神経へ伝達されて初めて収縮運動を起こすのが通常のメカニズムですが、場合によってはその信号がふくらはぎ内の一部の筋肉にしか伝達されないため、その筋肉部のみが過度に収縮するという異常な事態が引き起こされることがあります。
その異常な収縮により痙攣を起こしてこむら返りが起きます。
運動を長時間続けて疲れていたり、ウォーミングアップが不足していたり、体力が落ちていたりする時、運動不足などの時に起こりやすくなります。
特に高齢者の多くは慢性の運動不足のために常に腓腹筋が緊張した状態にあり、少し足を伸ばしたりふくらはぎを打ったりしただけでもこむら返りを起こすことがあります。睡眠時にも起こる場合が有ります。
上記のいずれの要因にも基づかない理由で発生するこむら返りがあり、それは他の疾病が原因として生じる可能性が強いことが指摘されています。
他の疾病の例としてこれまで指摘されてきたものとしては、腰椎椎間板ヘルニア、糖尿病、腎不全、動脈硬化、甲状腺異常、妊娠などが挙げられます。
なぜ寝ているときにこむら返り(足がつる)がおきるのか?
一般健康人でも激しい運動や長時間の立ち仕事の後には下肢を中心に起こることがありますが、50歳以上ではほぼ全員が一度は夜間のこむら返りを経験しており、60歳以上の6%が毎晩こむら返りに襲われているという報告もあります。
一般に、健康な人ならば過剰なイオンは尿や汗などから排出され、反応性がちょうどいい範囲内におさまるよう調節されています。
ところが、睡眠時は汗を多くかいており脱水傾向にあります。さらに全身をほとんど動かさないため、心拍数も減り、血行は低下しています。
夏場に冷房をつけっぱなしで寝たり布団をかけずに寝ると、足の筋肉が冷え血管も収縮し、血行はさらに悪くなります。
こういった悪い状況でイオンのバランスが崩れているときに、たまたま寝返りをうって筋肉に刺激が加わると、筋肉の細胞が暴走して過剰な収縮が発生しやすくなってしまいます。
ミネラルバランスの乱れ:カルシウムとカリウムは、筋肉の収縮や神経の伝達をスムーズにする働きがあり、この2つのミネラルを調整しているのがマグネシウムです。
3つとも大切なミネラルですが、特にマグネシウムの不足は腱紡錘の機能低下に大きな影響を与えます。
血行不良:体の冷えや座り仕事等による血行不良、寝ている間の血行の低下など。
筋力低下:高齢による自然なものがあります。
女性の場合、女性ホルモンの減少に伴う筋力低下も原因の一つ。
体温低下:夏の冷房や秋冬の体温低下があります。
眠る姿勢や環境:あおむけで重いふとんを使うことも原因となります。
水分不足:睡眠中にはコップ一杯の汗をかくと言われており、これが、睡眠時及び朝方につる原因の一つになります。また、お酒やコーヒーの摂り過ぎによる脱水も原因の一つです。
激しい運動を行う前にはストレッチ等の準備運動を行うこと
運動後・発汗後の水分補給や塩分補給を行うこと
それほど激しい運動をしない日常生活を送る場合でも、マッサージやストレッチなどを定期的に行うことで神経の一極集中を防ぐことが可能となります。
どういう人がなりやすいのですか?
運動中に起こることや、立ち仕事の多い人、高齢者、妊娠中の方に見られます。
しかしはっきりとした原因は分かっていません。
こむら返りは一般的に、急に体を動かしときに起こりやすい症状ですが、栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起きることがあります。
足を酷使したり筋肉疲労以外でも頻繁に足がつる場合、食生活の見直しやこまめな水分補給により体内のミネラルバランスが整うことで、症状の改善が期待できる場合があります。
さらに、足を冷やさないように温めたり、運動後のストレッチやマッサージも合わせて行えば、予防により効果的です。
寝ているときにこむら返り(足がつる)が起こる方は、ミネラルの補給と寝る前にコップ一杯の水を飲むようにしましょう。
リンパマッサージで免疫力をあげよう!
2023.12.13
今日は老廃物をスッキリ流してくれるリンパマッサージについてのお話しです。
よくお客様からリンパマッサージとはどんなマッサージなのかと聞かれることが多いため、まずリンパとは何かというところからリンパマッサージをご説明します。
リンパとは、血管のように全身に張りめぐらされたリンパ管と、その中を流れているリンパ液、リンパ管の中継地点であるリンパ節の総称です。
体内を流れる液体の代表的なものといえば血液ですが、リンパ液も体液のひとつです。まず、血管を流れる血液の大部分は、心臓から排出され、全身を巡って心臓に戻ります。大部分と記したのは、そのすべてが心臓に戻るのではなく、体内にある細胞の隅々に酸素と栄養を届けるために、一部は動脈側の血管から流出するからです。
そして、血管に戻れなかった水分はリンパ液となり、リンパ管を通って静脈に戻ります。
リンパ系の役割は大きく2つ。それは、細菌や異物が体内に入らないようにする免疫機能と体内の老廃物の回収と運搬を行う排泄機能です。この2つの役割を果たすうえで重要なのが、リンパ管の中継地点であるリンパ節です。
リンパ管の要所に位置するリンパ節は、体内に600〜800個あると言われ、首や脇の下、脚の付け根のあたりに多く存在します。リンパ節の中は、リンパ球やマクロファージといった白血球が充満しており、細菌や異物を取り込んで除去するフィルターのような働きを果たしています。
つまり、体内に侵入した細菌や異物はリンパ節でせき止められ、免疫によって処理されたうえで、きれいなリンパ液になって静脈で回収される
*リンパマッサージの効果
①老廃物の排出
老廃物を排出することは、人間の体にとって重要。
たとえば、ニキビや便秘、むくみなどの悩みは、体に老廃物がたまっていることが原因の可能性もある。
②浮腫の解消
むくみがひどくなるだけで、太ってみえたり、体が重くなったりします。
体が浮腫むことで内圧が高くなり圧迫感や痛み、酷いと痺れ感などが出る可能性もある。
③肩こりや腰の痛み
リンパには老廃物だけではなく、疲労物質を流す作用もある。リンパマッサージでは、硬くなった筋肉をほぐすことで、表面に浮いたリンパを流して、肩こりや腰の痛みの原因となる疲労物質を水分とともに排出してくれる。
④肌のくすみ解消
肌のくすみの大きな原因のひとつは血行不良。リンパにたまった老廃物を流すことで血行がよくなり、透明感のある肌をめざせる代謝アップ、痩せやすい体を作る
施術後は血流がアップするので、全身に栄養が行き渡り、排泄しやすい体へ。体内がよく巡回することで基礎代謝も上がりやすくなる。
*リンパマッサージを行う際は入浴後がおすすめ。
これは血流を良くした後に施術を行うことでよりリンパの流れがよくなり効果が上がりやすくなる。
*リンパマッサージがおすすめの方
汗かきにくい
︎︎︎︎風邪ひきやすい
︎︎︎︎運動不足
︎︎︎︎ストレスがたまっている
︎︎︎︎食事制限しても痩せない
︎︎︎︎足や手、顔がむくむ
︎︎︎︎冷え性
︎︎︎︎寝不足
︎︎︎︎肩こり・首こり
︎︎︎︎腰痛
*リンパマッサージはリラックスできる雰囲気を作る。
完全個室、照明は間接照明ほどの暗さ、リラックスできる音響など。
このように疲労回復、美容効果など体に良いことを全てご提供できるのがリンパマッサージです。
美容の在り方は今や老若男女関係ありません!
一人一人が自分らしく美容をたのしんでいけるように当院は精一杯お手伝いをさせていただきます!
鍼灸治療と東洋医学
2023.12.06
鍼灸治療は、いまや世界保健機関(WHO)からさ
まざまな症状に効果があると認められている、
世界中で認められた治療手法です。
知っているようで意外と知らない鍼灸治療につ
いてご紹介いたします。
身体の特定の点を刺激するために専用の鍼や灸
を用いた治療法のことをいいます。国家資格試
験である「はり師」「きゅう師」が施術の資格
を保有しています。
一般的によく治療に使われる鍼は髪の毛程度の
細さなので、熟練したはり師であればあるほど刺入した
ときの痛みはほとんどありません(ただし皮膚
には痛みを感じる点(痛点)があり、ごくまれ
にチクッとすることもあります)。
鍼灸といえば「頭痛、肩こりに効く」「東洋医
学」というイメージにとどまる方が多いのでは
ないでしょうか?
しかし、最近でも厚生労働省の発足したプロジ
ェクトチームでは西洋医学だけで対処できない
現代のさまざまな疾患に対して鍼灸治療も取り
入れた医療の促進を進めていくようになりまし
た。
また、中国、日本だけでなくアメリカ、ヨーロ
ッパでは日本以上に医療現場での活用が進んで
おり、もはや医学の東西という枠組を超えて、
人々にとって重要な医療手法としてグローバルに認識されています。
長い歴史をもつ鍼灸治療
鍼灸の歴史は大変深く、紀元前の中国ではすで
に鍼治療が広く流行したという文献も残ってお
り、約2000年以上の長い歴史がある伝統医学で
す。
日本では奈良時代に伝えられたとされ、江戸時
代には庶民にも広まったとされています。
戦後には現在の「あん摩マッサージ指圧師、は
り師きゅう師などに関する法律」の原型である
法律が制定され、日本の鍼灸はより科学的な裏
付けが強く求められるようになり、研究も学会
レベルで進められるようになりました。
日本の鍼は、中国の鍼と異なり非常に細い鍼を
用いています。太い鍼の方が効果があるとされ
ていますが、その代わり痛みが強いのが特徴で
す。痛みに敏感な日本ではあまり普及せず、杉
山和一という人物が考案した管鍼法という、細
い鍼と管を組み合わせた鍼治療が一般化して現
在に至っています。
東洋医学と鍼灸治療の仕組み
西洋医学では病気の原因に着目し、その原因を
除去することで病気を治療するというアプロー
チ方法をとりますが、東洋医学では病気を体全
体のバランスが崩れていることから症状が生ま
れ、そのバランスを自然治癒力により戻すこと
ができれば病気が治る、という考え方をしてい
ます。基本的な考え方として「気・血・水」の
バランスが保たれている状態が健康状態であり
、気・血・水のバランスの崩れ方によって治療
法が定められており、鍼灸では2000以上のツボ
を症状に応じて使い分けるのです。
「気」
体内を流れるエネルギーのことで、元気や気力
の『気』という意味をもちます。
「血」
文字通り血液のこと。血液が循環して全身に栄
養を運び、潤いを与えます。
「水」
血液以外の体内にあるリンパ液やその他の水分
のこと。消化や排泄に影響するほか、臓器をス
ムーズに働かせる潤滑油のような作用もありま
す。
このうち、「気・血」が体内を巡るための通り
道のこと経路」と呼びますが、これこそが
鍼治療の重要なポイントである「経穴(ツボ)
」の集合体にあたります。経絡が滞らないよう
に、また滞った経絡を改善するために、経絡の
各所にあるポイント「経穴(ツボ)」に鍼や灸
を施すことで、「気・血」の流れをスムーズに
することが鍼灸治療なのです。
このような西洋医学との違いはありますが、病
気の根本的な原因を除去する、という目的はど
ちらも共通しており、同じ医学の異なる領域と
して、医療の分野では使い分けていくことがべ
ストであると考えられます。
根本治療とは
2023.11.22
本当の『根本治療』をご存知ですか?
マッサージ、骨盤矯正、筋膜リリース、鍼灸治療…
健康業界において、様々な治療技術が
時代の流れと共に発展し、進化を遂げています。
どの技術も素晴らしいもので、先人の先生方が
1人でも多くの患者様を元気にしたい
という思いが形になった努力の賜物です。
しかし、痛みでお困りの方が無くならないのはなぜでしょうか…
我々、治療家の永遠の悩みです。
マッサージも、骨盤矯正も、筋膜リリースも、鍼灸治療も
ダメと言っている訳ではありません。
しかし、
マッサージだけでは
骨盤矯正だけでは
筋膜リリースだけでは
鍼灸治療だけでは
対応できなくなっているからです。
ヒトが生まれながらにそれぞれDNAが違うように
お身体の持つ特性(素質)が違うので
素晴らしい技術にも「合う」「合わない」が存在するのです。
この、ヒトが生まれながらに持つ「素質」を
先人の先生方がコツコツと積み上げてくださったおかげで
統計学上で知る事ができるようになりました。
私自身が有名な先生方のように
何か特別な技術を極めている訳ではありませんが
患者様の持つ「素質」に基づいて
あなたにあった治療の入り口をお教えする事ができます。
知りたい方はこちらへ https://lin.ee/DdqPDCp