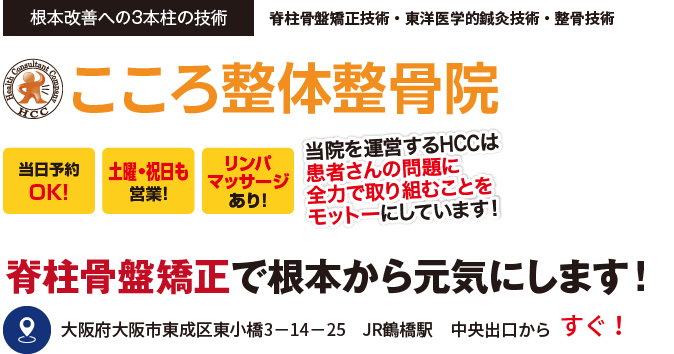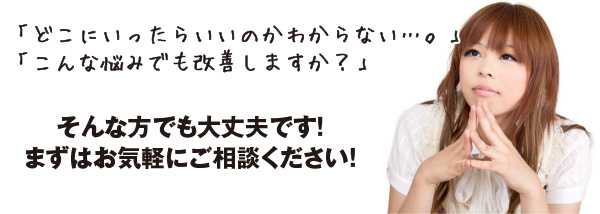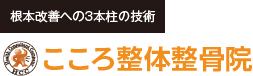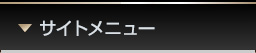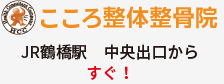お風呂について
2022.08.12
入浴するとき、暑い日や忙しい日はシャワーだけでいいやとなっておられる方は多いのではないでしょうか?
しかし、実はお風呂には、私たちが思っている以上に、健康面で大事なことがたくさんあります。
お風呂と健康について本日はお話したいとおもいます。
お風呂の最大の効果は血行促進にあります。湯舟につかると体が温まってゆったりした気持ちになりますね。
これを温熱効果といいます。
体が温まると血管が広がり血行がよくなります。
これにより体内の老廃物や疲労物質が排出されるのを促進することができます。
つまり新陳代謝がよくなり、体の内側から健康できれいになれるのです。
湯舟の中の水圧も血行を促進するのに大きなやくわりを果たします。
ほかにも湯舟の中の浮力で体にかかる重力が軽減されて筋肉の緊張がほぐれます。
そのほかにも温熱効果には、自律神経のバランスを整える効果があります。自律神経とは私たちが生きていくうえで無意識に働いている神経のことです。
脳や体を活発に動かす交感神経と逆にゆっくりリラックスさせるための副交感神経があります。
お風呂に入ると副交感神経が優位になり心身をリラックスさせることができます。
副交感神経が優位になると胃や腸の働きも活発になるので便秘やお腹の悩みの解決にもつながります。
そして何より大事なのは睡眠の質が上がるという事です。
お風呂にゆっくり入ると体温は上昇します。
そのまま高い体温を維持すると体に負担がかかるので副交感神経はたいおんをさげるように働きます。
この働きは人間の体が体温の低下により眠りにおちる働きとうまくマッチして睡眠に入る良い傾斜をつくってくれます。
効果を上げる入浴方法
ここまで上げたようにお風呂には体に良い効果がたくさんあります。さらに効果を上げるには正しい入浴方法に従っていただくとよいです。まずはたっぷり水分補給。
脱水症状を防ぐため入浴前はコップ1~2杯のお水、お茶、スポーツドリンクをお取りください。お酒は血圧の急激な上昇の恐れがある為おひかえください。
血行の急激な上昇を防ぐため手桶で10杯ほどかけ湯をしてください。
忙しすぎて湯船につかれない方は足湯だけでも大丈夫です。シャワーだけでは体の温まりが十分ではないので、42度~43度のお湯を手桶に張り足先を入れながら体を洗ってください。
人間の体を流れる血液は約1分間で全身を一周するといわれています。
体を洗ってる間に末端を温めるとより体内循環の効果が上がるので体内環境とリラックスこに効果的です。
このようにたかがお風呂と思ってシャワーだけにするよりしっかり湯舟につかる方が健康づくりには良いですよ!
一日頑張り続けた体を夜はゆっくり休めて、暑い夏を乗り切りましょう!
夏バテ
2022.08.10
夏バテについて
夏真っ盛り!暑い日が続きますが、「疲れが取れない」「食欲がわかない」「眠れない」「無気力」などの症状に悩まされたりしていませんか?
それはいわゆる「夏バテ」かもしれません。
本日は陥ると辛い夏バテについてお話ししていこうと思います。
夏バテとは一体どういうものなのか?夏バテとは、夏季の高温、多湿にからだが対応できず起こる体の不調の総称です。
脱水や栄養不足、自律神経の乱れにより体の機能が調節できなくなっている状態などが当てはまります。
とくに高齢者は若年層と違い体内の水分量がもともと少ないため、少しの脱水で動悸や息切れをおこすことがあります。
食欲の減退によりさっぱりした軽いものばかり食べていると栄養不足に陥ります。
外は猛暑のためエアコンの効いた部屋にずっといると体温の調節が出来なくなり自律神経の乱れにつながります。
このように暑さに対して生活習慣が元でどんどん体調が悪くなってしまうのがなつばての特徴です。
それではどのような人が夏バテになりやすいのでしょうか?
①夜ふかしすることが多い、夜遅くまで起きていると自律神経が乱れる原因になり体温調節や循環の調節が弱くなります。
②冷房の温度を低めに設定している、エアコンによりからだを冷やしすぎると外気の気温の変化に身体が対応しきれなくなり体調不良の原因になります。
③お風呂が湯船に浸からずシャワーだけですます、人間の体は体温が下がると自然と眠たくなるようにできています。お風呂で湯船に浸かると体内の温度が上がり、その後温度が下がっていくため睡眠にはいるための良い傾斜ができます。そのため質の良いすいみんがとれて体力の回復に繋がります。シャワーだけだとからだの表面だけの温度が上がり睡眠のしつが悪くなります。
④睡眠不足、睡眠不足はきせつを問わず自律神経の乱れにつながります。
⑤運動不足、運動は体力をつけるためだけのものではなく、自律神経の調節にも良いです。運動不足になると自律神経の乱れと体力の低下が起こります。
⑥冷たいものをとりすぎる、冷たいものをとりすぎると胃腸の働きが悪くなり、栄養分の吸収が弱くなるため栄養失調が起こります。体力の低下も引き起こすので、体調不良の原因になります。
⑦食事の偏り、肉や野菜の摂取量、バランスが偏ると疲労回復に必要な栄養分が不足するために体力の回復に支障が出ます。
夏バテはひごろの生活習慣の見直しで予防することができます。睡眠をしっかりとる、冷房でからだを冷やしすぎない、入浴時は湯船にしっかり浸かる、適度な運動を心がける、こまめに水分をとる、栄養バランスの良い食事をとる、など規則正しい生活を送り、朝は朝日をしっかり浴びて朝食を取り、よるは早く睡眠をとることを心がけましょう。今回挙げた内容は夏バテに対してのほんの一部の知識ですが、まずは水分不足にならないこと、体の不調を感じたらすぐに休養をとること、睡眠をしっかりとる、栄養バランスのとれた食事をとること、体力をしっかり温存し、無理をしないよう心がけて暑い夏を乗り切りましょう!
こむら返り
2022.08.01
足がつる、いわゆる「こむら返り」の経験は誰にでもあると思います。
運動時だけでなく、就寝中に突然、足がつった驚きと痛みで目が覚めることもありますが、おさまるのをひたすら待つくらいしか出来ないのは非常に辛いものです。
「つる」とは、足や手などの筋肉が伸縮バランスを崩してしまうことで、異常な収縮を起こし、元に戻らない状態をいいます。
一般的に、急に体を動かしたときに起こりやすい症状ですが、栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起きることがあります。
たまに発生するくらいならそこまで気になりませんが、足を酷使させたわけでもないのに、生活に支障をきたすほど頻繁に起きる場合、筋肉疲労以外にどんな原因が考えられるのでしょうか。
こむら返りや足がつる原因や対策について詳しく解説していきます。
こむら返りとは
ふくらはぎに起きる筋肉のけいれんの総称です。
足がつることもこれにあたります。
基本的には病気ではありません。
ふくらはぎの腓腹筋が異常な緊張をおこし、筋肉が収縮したまま弛暖しない状態になり、激しい痛みを伴う症状です。
ちなみに、こむらがえりの「こむら」はふくらはぎのことを指します。
その名の通り、ふくらはぎに多く起こりますが、実は、足の裏や指、太もも、胸など、体のどこにでも発生します。
運動中や就寝中に発症することが多く、妊娠中や加齢によっても起きやすくなります。
こむらがえりを起こすと、強い痛みを伴いますが、ほとんどの場合は数分間でおさまります。
どうしてこむら返り(足がつる)は起きるのですか?
大脳から発信された信号が脊椎中の神経系を通り、ふくらはぎへと直結する末梢神経へ伝達されて初めて収縮運動を起こすのが通常のメカニズムですが、場合によってはその信号がふくらはぎ内の一部の筋肉にしか伝達されないため、その筋肉部のみが過度に収縮するという異常な事態が引き起こされることがあります。
その異常な収縮により痙攣を起こしてこむら返りが起きます。
運動を長時間続けて疲れていたり、ウォーミングアップが不足していたり、体力が落ちていたりする時、運動不足などの時に起こりやすくなります。
特に高齢者の多くは慢性の運動不足のために常に腓腹筋が緊張した状態にあり、少し足を伸ばしたりふくらはぎを打ったりしただけでもこむら返りを起こすことがあります。睡眠時にも起こる場合が有ります。
上記のいずれの要因にも基づかない理由で発生するこむら返りがあり、それは他の疾病が原因として生じる可能性が強いことが指摘されています。
他の疾病の例としてこれまで指摘されてきたものとしては、腰椎椎間板ヘルニア、糖尿病、腎不全、動脈硬化、甲状腺異常、妊娠などが挙げられます。
なぜ寝ているときにこむら返り(足がつる)がおきるのか?
一般健康人でも激しい運動や長時間の立ち仕事の後には下肢を中心に起こることがありますが、50歳以上ではほぼ全員が一度は夜間のこむら返りを経験しており、60歳以上の6%が毎晩こむら返りに襲われているという報告もあります。
一般に、健康な人ならば過剰なイオンは尿や汗などから排出され、反応性がちょうどいい範囲内におさまるよう調節されています。
ところが、睡眠時は汗を多くかいており脱水傾向にあります。さらに全身をほとんど動かさないため、心拍数も減り、血行は低下しています。
夏場に冷房をつけっぱなしで寝たり布団をかけずに寝ると、足の筋肉が冷え血管も収縮し、血行はさらに悪くなります。
こういった悪い状況でイオンのバランスが崩れているときに、たまたま寝返りをうって筋肉に刺激が加わると、筋肉の細胞が暴走して過剰な収縮が発生しやすくなってしまいます。
ミネラルバランスの乱れ:カルシウムとカリウムは、筋肉の収縮や神経の伝達をスムーズにする働きがあり、この2つのミネラルを調整しているのがマグネシウムです。
3つとも大切なミネラルですが、特にマグネシウムの不足は腱紡錘の機能低下に大きな影響を与えます。
血行不良:体の冷えや座り仕事等による血行不良、寝ている間の血行の低下など。
筋力低下:高齢による自然なものがあります。
女性の場合、女性ホルモンの減少に伴う筋力低下も原因の一つ。
体温低下:夏の冷房や秋冬の体温低下があります。
眠る姿勢や環境:あおむけで重いふとんを使うことも原因となります。
水分不足:睡眠中にはコップ一杯の汗をかくと言われており、これが、睡眠時及び朝方につる原因の一つになります。また、お酒やコーヒーの摂り過ぎによる脱水も原因の一つです。
激しい運動を行う前にはストレッチ等の準備運動を行うこと
運動後・発汗後の水分補給や塩分補給を行うこと
それほど激しい運動をしない日常生活を送る場合でも、マッサージやストレッチなどを定期的に行うことで神経の一極集中を防ぐことが可能となります。
どういう人がなりやすいのですか?
運動中に起こることや、立ち仕事の多い人、高齢者、妊娠中の方に見られます。
しかしはっきりとした原因は分かっていません。
こむら返りは一般的に、急に体を動かしときに起こりやすい症状ですが、栄養不足や水分不足、冷え、熱中症、急激な寒暖差が原因で起きることがあります。
足を酷使したり筋肉疲労以外でも頻繁に足がつる場合、食生活の見直しやこまめな水分補給により体内のミネラルバランスが整うことで、症状の改善が期待できる場合があります。
さらに、足を冷やさないように温めたり、運動後のストレッチやマッサージも合わせて行えば、予防により効果的です。
寝ているときにこむら返り(足がつる)が起こる方は、ミネラルの補給と寝る前にコップ一杯の水を飲むようにしましょう。
コロナウイルス感染拡大について
2022.07.28
こんにちは、鶴橋こころ整体整骨院で管理鍼灸師をしております、石本と申します。
ここ最近、新型コロナウイルス感染拡大のニュースが日々放送され、不安感を抱えていらっしゃる方も多いのではと思います。
コロナウイルスの症状はかかった人によって一人一人違っていたり、無症状ですむ場合もあれば、重症化してしまう場合もあり私自身も医療に関わる人間としてお恥ずかしいお話しですが、その実態については無知と言って良いです。
防止策としては行動の制限や職場、自宅、公共機関での新しい制度を守る事があげられていますが、色んな人がいて、色んな状況やシチュエーションの中すべてを守って行動する事が難しい場合も存在するのではないかと思います。
かと言って感染に対する恐怖心を捨てられるかと言うのは無理な話で、私はもちろん、誰だって感染するのは怖いはずです。
私個人、一鍼灸師としてこのような事態に対して困っている、不安を抱えていると言う方の手助けになれることはないのかと考えた時に、やはり形を変え進化し続けるウイルスを寄せ付けない免疫力を持った体質になっていってもらう身体作りのお手伝いをさせていただく事が微力でも出来ることではないかと考えています。
鍼灸治療はもともと人間の身体が本来持っている自然治癒力を高めるための手技です。いかなる外敵が体に侵入してきても強い免疫で感染を防げる体になってもらうことを目的とします。
これからの社会にはさまざまな考え方を個人個人が持つことになり、コロナウイルスに関してもウィズコロナという考え方もあります。
どのような社会になったとしても、その人が自分らしく感染や風潮を恐れることなく楽しく生活を送ってもらえたら良いなと思っています。
鶴橋こころ整体整骨院は、先程ご説明した鍼灸治療もふくめ、整体、全身もみほぐし、リンパマッサージなど一人一人に適した施術をご提供できる、トータルヘルスケア専門院です。
身体の中に備わっている自然治癒力を上げていくために普段からのお身体のお悩みにもしっかりお話をお聞きして一番良い最善の方法を一緒に考えていきたいと願っています。
体が何故か重だるいな、気力が出ないななど、何故かわからないが体調が悪く感じるなどのご相談でも結構です。
ずっと苦しんでいたお悩みの解決とこれから元気になってもらう重要な糸口にもなるかもしれません。
いつでもご相談ください。
まだまだ暑い日は続き、コロナの問題もありますが、お身体だけにはお気をつけて無理なくおすごしください。
脱水症状
2022.07.16
こんにちは、鶴橋こころ整体整骨院で管理鍼灸師をしております。
石本と申します。
ここ数年での新型コロナウイルス感染拡大問題も少しずつ緩和されていき新しいルールや習慣のもと、いよいよ夏本番を迎えます。
皆様予定はお決まりですか?
海や山、プールにイベントなどお出掛けする機会が増える時期ですが、注意が必要になるのは炎天下での脱水症状です。
脱水症状は突然やってきます。
自覚症状が現れる時にはすでに危険な状態におちいっていることもあり、命に関わることもあります。
脱水症状とはどのような状態になるのでしょうか?
人間のからだは体内に蓄える水分量と、体外へ放出する水分量とのバランスで体液を調節します。
このバランスが崩れたときに脱水症状が起こります。
発汗、下痢、嘔吐など様々な原因はありますが、脱水症状が起こると意識か混濁し、頭痛、吐き気、めまいを引き起こします。
こまめな水分補給が必要になりますので本日は脱水症状をどうやって予防していけば良いのかを説明させていただきます。
まず大事なのは水分補給です。ペットボトルなど持ち運びやすく量がわかりやすい容器にいれた水分を常に準備しておく必要があります。
脱水症状には自覚症状が現れる前段階の前脱水と言う状態があります。
体内の水分が3%減ると脱水症状に対して、2%減っている段階を前脱水と言い、いわゆる夏バテのような倦怠感を感じている状態がこれにあたります。
体が重い、ダルいといったような症状を感じたらその時点で水分をとらなくてはいけません。
特に注意が必要なものとしては高齢者の脱水症状です。
お一人で暮らしている高齢者の方などエアコンを使わない方は知らず知らずのうちに室温が上がっていることに気付かず、自覚症状が感じられない場合がおおいです。
空調による室温調節と決まった時間に水分補給を行うことが大事です。
これからの時期はどんどん気温もあがり、発汗が激しくなることが考えられます。
これくらいならと自分の身体を過信せず、体調管理と健康維持に注意していくことで、元気に夏を楽しむ努力が必要です。
皆様も連休やお盆休みなど大型連休にむけて楽しい思い出をいっぱいご家族やお友達と作っていきたいと思います。
楽しみにでかけた先で事故が起こらないよう脱水症状に対する正しい知識をたくわえ、元気に夏を乗り切りましょう!
鶴橋こころ整体整骨院はトータルヘルスケア専門院として皆様が元気で健やかな日々を送っていただけることを常に考え、地域貢献に役立てるよう、精一杯がんばります。
熱中症
2022.07.14
熱中症とは高温多湿な環境に私たちの体が順応できなくなっておこる反応の総称です。このような症状が起こった場合熱中症になっている可能性があります。めまいや顔のほてり、筋肉痛や筋肉のけいれん、カラダのだるさや吐き気、汗のかきかたがおかしい、体温が高い、皮膚の異常、呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない、水分がとれない、などの症状が起こった場合非常に危険な状態です。熱中症の代表的な初期症状としてはめまいや立ちくらみがおこります。これは熱失神とよばれるものです。暑さで体温が急激にあがると、体にこもった熱を逃そうとして皮膚の血管がひろがります。その結果、全身の血流量が減ることになりけつあつが下がってしまいます。血圧がさがると、一時的に脳への血流が減るため、熱失神がおこりやすくなります。そして体温の上昇により、汗が大量に流れ出る、あるいは全く汗が出ない状態になります。これは、体温調節機能が働かなくなってしまい、正常な発汗ができない状態です。熱中症の初期症状では、それほど体温が高くならないこともあります。表面的には判断できないことも多く、最初は軽症でも重症化する危険性があります。体温が普段よりも1度以上高い場合には、熱中症の初期症状としての注意が必要です。体温を下げようとして大量の汗をかくと体内の水分と塩分が体外に排出されます。塩分の欠乏により、筋肉痛や筋肉の硬直がおこります。いわゆるこむら返りの事でこれを熱けいれんと呼びます。典型的な熱中症の初期症状は他にも手足に熱けいれんがおこることがあります。その他に注意が必要な例として頭痛や吐き気、疲労感があります。軽い不快感として感じることもあり熱中症と気づかないおそれがあります。熱中症の初期症状が疑われた時はすぐ適切な対応をとらなくてはいけません。まず涼しい場所に移動する。屋外なら木陰など安全で涼しい場所に移動します。屋内ならエアコンや扇風機のある場所に移動、自分の足で歩けそうでもふらつきや一時的な失神で転倒などの心配があります。助けてもらえる状況なら自分の身体を過信せず必ず誰かにたすけを求めて体を支えてもらい移動してください。からだの中に熱がこもっている可能性があるので体を冷やします。衣類の襟元を緩めて風を通りやすくして。脇の下や足の付け根、首筋や足首を氷や氷嚢で冷やしてください。水分を大量に体外へ排出している可能性があるので水分と塩分もしっかりとってください。、
デスクワークの方へ 簡単なストレッチ
2022.06.26
こんにちは、鶴橋こころ整体整骨院のブログをいつもご愛読いただきありがとうございます。
今回は前回に引き続き、デスクワークによるお身体のお悩みにフォーカスを当てていきたいと思います。
在宅ワークなどにより外出が減り、運動不足になりやすい方も是非ご参考にしていただければ光栄です。
長時間同じ姿勢をとると筋肉が緊張し続け、血流が悪くなり、筋肉がさらに硬くなるという負のスパイラルが起こり、肩こりや首こり・腰痛といった症状を引き起こします。
そこで、だれでも簡単に空いた時間でできるストレッチをご紹介します。
デスクでできる簡単ストレッチ
正しい姿勢であっても、長時間同じ姿勢を取り続けることは身体への負担になります。
そのため30分から1時間に1度は立ったり、ストレッチをやってみたりして、身体をいたわってあげましょう。
ここでは、座ったままでもできる簡単なストレッチを紹介します。
肩と胸を開くストレッチ
作業に集中していたら、いつの間にか背中が丸まり前かがみになっていることはよくあります。
そんな時は胸と肩の筋肉が硬く緊張して固まっている場合があります。
①体の後ろで手を組み胸をはります。
②大きくゆっくりと呼吸をします。
③この時に首の前の筋肉も伸びるように少し上を向くとより効果的です。
作業がひと段落する度に、この肩と胸を開くストレッチを行いましょう。
腰のストレッチ
①椅子に浅く腰掛け、背すじを伸ばします?
② 左足は膝を伸ばして前に出し、右膝
は90曲げます。
③ 背骨が丸まらないように、上半身を
前へ傾ける、ハムストリングスが伸びているところで止めます。
④ゆっくり呼吸しながら15秒程度キー
プします。
⑤反対側も同様に行います。
ハムストリングスが硬い人は、膝を曲げて行っても構いません。痛みのない範囲で行いましょう。
まとめ
デスクワークで長時間同じ姿勢をとっている方やテレワークになってパソコンで作業をする時間が増えた方は、肩こりや腰痛の理由や原因を理解した上で、正しい姿勢のポイントを押さえることが重要です。
また、自分に合った適切な机と椅子を選び、パソコン作業の合間には簡単なストレッチを行いましょう。
前回、今回とお伝えさせていただいたデスクワークによる身体の痛みですが何か一つでも、これは私のことじゃないか?これは僕に当てはまるなと感じたらいつでもご相談ください。